「いす取りゲーム」と「カフカの階段」の比喩について
(2002.10.16〜20)(2002.2.7 カフカの階段を一部変更)(2006.8.2 一部追加・変更)
| (野宿問題の授業のための) 「いす取りゲーム」と「カフカの階段」の比喩について |
この二つの比喩は、もともとは「野宿に至るのは自業自得」、そして「野宿者が仕事と住居のある生活に復帰することがなぜ難しいか」ということに対する解答例として考え出した。
授業でよく使っているが、「わかりやすい」「シンプルで強力」と好評な模様。
実際の狙いは、「いす取りゲーム」+「カフカの階段」によって、就労と野宿をめぐる現状をモデル化し、別の可能性を示唆することにある。
(なお、「いす取りゲーム」と「カフカの階段」は、授業などで自由に使っていただいて結構ですが、どこの学校のどのような授業で使ったかを報告していただけるとありがたいです)。
![]()

| ■「いす取りゲーム」■ |
▼
「いす取りゲーム」の譬えを最初に使ったのは2001年9月の大阪YMCA国際専門学校・国際高等課程での授業「野宿者襲撃」でだった。そのときの模様は以下の通り。
生徒の質問の一つは、先週授業に来た野宿者の一人が、「こうなったのは自業自得や。みんな、おっちゃんみたいになっちゃあかん」と言ったことを引いて、「やっぱり野宿になるのは自業自得ではないかと思うんですが」というものだった。 ぼくはこう答えた。個人の努力の問題と社会の構造の問題は別だ、と。例えば「いす取りゲーム」を考えてみよう。人数に対していすの数が足りなくて、音楽が止まると一斉にいすを取り合うあのゲーム。この場合、いすとは「仕事」のことだ。仕事がなくなれば、収入がなくなり、いずれは家賃も払えなくなり、最後には野宿に至るというのは当然な話だ。さて、確かにいす取りゲームでいすをとれなかった人は「自分の努力が足りなかった。自業自得だ」と思うかもしれない。けれども、いすの数が人数より少ない限り、何をどうしたって誰かがいすからあぶれるのだ。仮にその人がうんと努力すれば、今度は他の誰かのいすがなくなってしまう。仮りに、すべての人が今の100倍努力したとしても、同じ人数がいすを取れないことでは全然変わりがない。要するに、問題は個人の努力ではなくて、いすの数の問題、つまり構造的な問題なのだ。今、失業率が5%を越えているが、これは要するに、いすの数が極端に不足している状態だ。われわれがやっていることの一つは、いすの数を増やせと行政に要求することだ。いすの数を増やせるのは、一応は行政しかないのだから(実際は「です・ます」体)。 |
▼
いす取りゲームは、ここでは「就労」の比喩、そして同時に「競争社会」についての比喩として使っている(ネットで検索すればわかるが、よく使われている比喩である)。例えば、いす取りゲームの譬えは特に「受験競争」について当てはまる。
さらに、ここ数十年については、「学歴が低いと失業率が高い」という事実が知られている。つまり、(受験)競争の敗者が(就労)競争の敗者になりやすい、ということである。近代国家では、「学校」が特に資本主義「企業」への人材育成機関として機能してきたことを考えれば、それは当然の事である。
▼
しかし、実際には「いす取りゲーム」は「競争」の比喩として適切とは言えない。つまり、音楽が止まったときにいすを取り合うあのゲームは、その勝敗をほとんど「偶然」にまかせている。「いすの前で足踏みする」、「人を暴力で押しのけて座る」といった違反行為がなければ、いす取りゲームは体力や学力にほとんど関係しない、むしろ非常に公平なゲームと言える。その意味で、いす取りゲームは「くじ引き」をゲーム化したものに近い。われわれがいす取りゲームをしたとき感じる一種の爽快感は、この「公平」さのためなのだろう。
「競争社会」の比喩としては、本当は「いす取りゲーム」よりも「ビーチフラッグ」の方が適当だろう。後ろ向きに腹這いになり、スタートの合図とともに遠くの旗を取り合うあのゲーム。これは明快に体力の「強い者」が勝つゲームである。しかも、現実社会に当てはめて考えれば、スタート地点自体、すでに格差が作られている。つまり、家庭において「資産」がある、あるいは両親の「学力」が高いこどもが、その後の学力競争に関してかなり有利であることはよく知られている。スタート地点ですでに格差があるわけである。こうして、ある程度以上のスタート格差が生じた場合、不利な立場の者の一定部分は、「競争」を早々とあきらめて「今を楽しむ」方向に向かうことになる。(これは「まったり」とか言われている)。
以上のような事情にもかかわらず「いす取りゲーム」の譬えを使うのは、ひとえにその「わかり易さ」のため、そしてより重要な点として、失業や野宿に陥るのは「たまたま」だったのではないか、何らかの要因がたまたま重なれば誰でもそうなる可能性があったのではないかということを暗示するためである。つまり社会における「偶然」性の問題を示す意味がある。
▼
授業の中で、「仮りに、すべての人が今の100倍努力したとしても、同じ人数がいすを取れないことでは全然変わりがない」と言ったが、いすを取るために「仮に1000倍、100万倍努力」しても、もちろん結果はまったく同じである。結果が同じだとすれば、この「1000倍、100万倍」の努力はまったく「無駄な努力」だったということになる。
とすると、仮に音楽がなかなか止まらなくて、なおかつ参加者が「100万倍の努力」をしていれば、いずれゲームの参加者はばたばたと「過労死」してしまうかもしれない。そして、ゲームは「いすの数」と「人間の数」が同数になるときに終了するだろう。これはブラックジョークではない。現実に、野宿者の多くは仕事を求めても得られず、その結果として野宿に至り、最悪の場合に路上死している。
▼(この項、2006年8月に追加)
いす取りゲームの話は、失業率と野宿問題に関する比喩だったが、もちろん「正社員」のいすの取り合いと考えることができる。2006年現在、失業率が改善しているが、これはよく知られているように、そのほとんどが、人権費削減のために多くの企業が正社員数を絞り込んでパート・アルバイトなどの不安定就労層を増やした効果だった。つまり、いす取りゲームは「就労―失業」から「正規雇用―不安定雇用」へとその軸を移動していると考えられる。
2006年6月の朝日新聞のインタビューで竹中大臣が、「不良債権を処理せずに放っておいたら、いま二百数十万人の失業者が、たぶん400万〜500万人になっていた。所得ゼロの人がそれだけいたら、格差はもっと拡大していたでしょう。経済をよくすることは格差を縮めることです。小泉内閣はまさにそれをやったんです」「格差ではなく貧困の議論をすべきです。貧困が一定程度広がったら政策で対応しないといけませんが、社会的に解決しないといけない大問題としての貧困はこの国にはないと思います」と言っていた。
(「社会的に解決しないといけない」「貧困はこの国にはない」って!)。
しかし、実は90年代以降のいわゆる「ニューエコノミー」期のアメリカでも、経済成長と失業率の改善が顕著だった。しかし、極限の貧困であるホームレス問題はその中でも進行し続けていた。失業率の「いす取りゲーム」から、正社員と不安定就労層あるいは低所得層の「いす取りゲーム」への軸移動があっただけで、結果として絶対的貧困の問題が解決されたことはない。多分、日本はその方向をまっしぐらに追いかけている。
▼
「いす取りゲーム」の比喩を使って野宿者の「自業自得論」について触れたとき、生徒の感想には次のようなものもあった。
「でもそのいすにすわれなかった人は、どりょくがたりないと思う。あまった2人は、つぎのいすとりゲームをしたらいいと思う。それでもすわれない人は、ひっしにしてないと思う。人間死ぬきでしたらなんでもできる。人生勝組になる!!」
「自分は、余った人には絶対ならないようにがんばろうと思った」
しかし、こうして競争のゲームに乗っかって「死ぬ気で」「がんばろう」としても、全体の結果は変わらないとすれば、それは無意味かもしれないではないか。そうではなくて、むしろゲームの規則を変えてはどうか、という話がありえるわけである。
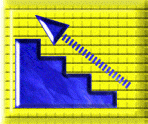
| ■「カフカの階段」■ |
次のカフカの文章を読んでもらい、イメージを作ってもらう。
|
|
カッコの中に何が入るか、しばらく考えてもらう。
|
■この結果、一段一段落ちて「野宿の状態」に至った野宿者は、元の生活に復帰するためには幾つかの条件を一気にクリアしなければならず、自力では事実上、復帰不可能となっている。このため、現在、野宿者は増える一方になっている。 |
▼
この「カフカの階段」の図は、階段を手で描いたあと、ありむら潜の「カマやん」シリーズからあちこち切り抜いて貼って作った(06年1月、コメントを一部変更。2月、絵を一部差し替え)。ありむらさんは、運動用途のためならマンガも無断使用OKとされているので、使わせていただいている。
なお、カフカの引用は有名な「父への手紙」からだが、この比喩はもともとは結婚問題について言われていた。読んだとき「うまい比喩だなあ」と感心したが、あとになって「これは野宿者問題の比喩に使えるな」と気がついた。すなわち、いったん野宿に至った人が、野宿から脱することがなぜ難しいのか、ということをイメージとして示そうということである。(われわれの社会は「カフカ的」なのである!)。
▼
階段から落ちるときには、通常は「網」が張ってあって、滑り落ちても助かるようになっている(はず)。つまり、「雇用保険」「健康保険」などの「セーフティネット」のこと。「セーフティネット」は言葉通り「網」であって、階段から落ちるのを防いでくれる。
しかし、こうしたセーフティネットが完備されているのは主に「正社員」に限られており、「日雇労働者」「パート・アルバイト労働者」はその点で非常に不備な状態にある。何かの怪我や病気でたちまち生活に困ってしまうわけである。
しかも、日雇労働者、パート・アルバイト労働者は、「いつ首を切られるかかわからない」(つまり、いつ階段からおちてもおかしくない)状況にある。
▼
先に触れたように、統計上、学歴が低いと失業率が高い。競争社会(受験競争も含む)の敗者が不安定就労になり、野宿するというシステム。
おまけに、こうした不安定就労層は差別を受けている。
事実、野宿者が差別される(「話しかけられても無視しなさい」「くさい、きたない」「働く気がない」)ように、不安定就労層は、日雇いもフリーターも、「いつまでブラブラしているの」「そろそろきちんとした仕事に就いたら」「長くやってる仕事じゃない」「いつまでもこんなことじゃだめなんだから」等々、周りの人からしつこく言われるらしい。「職業に貴賤はない」という話はウソだったのである。それを変えねばならない。少なくとも、競争の敗者を差別し、さげずむ社会の姿勢を変えねばならない。
|
|
▼
この階段の譬えの狙いの一つは、野宿者問題の解決のためには、「段差を作る」ことが、つまり「衣・食・住」にわたる行政や市民の援助が必要だ、ということである。野宿者個人ががんばれば自力でなんとかなる、という話ではない、ということだ。
そして、野宿者の「社会復帰」を目的とした2002年施行の「ホームレス自立支援法」は、最もうまくいった場合(多分そうはならないが)、この「段差」づくりのための法律として機能するはずである。
|
ところで、「階段の上では何をやっているのかな?」 普通の答えは、「仕事と家のある元の生活」である。しかし、ここでの答えは「上ではいす取りゲームが行われている」というものだ。 「いす取りゲーム」+「カフカの階段」、これが現在の日本の就労と野宿の現状である。 |
![]()
| 「いす取りゲーム」+「カフカの階段」、これが現在の日本の就労と野宿の現状である |
|
|
▼
もちろん、これはおおざっぱな話で、現実には野宿者が一人就職したからといって他の一人が失業するわけではない。また、なんらかの職業訓練によって、従来は人手のなかった職種に野宿者が進出できれば、それはいわゆる摩擦的失業の解消であって、望まれるべき解決となるだろう。
しかし、ここで言うのはマクロな視点から見た話である。つまり、現在、大阪にいる1万5000人程度の野宿者がただちにどこかに就職できるような状況は全くない。つまり、1万5000人が階段を上がれば大体同数が階段から落ちる他ない。職業訓練についても同様で、現在55才を平均とする多くの野宿者が、比較的人手の少ない、例えばコンピュータ業界やサービス業界に再就職できるかどうかはきわめて疑問なのだ。
▼
だとすれば、問題は「いす取りゲーム」の規則そのものを変える、という方向になるだろう。競争のゲームに乗っかって「死ぬ気で」「がんばろう」としても、全体の結果は変わらないとすれば、それは無意味である。むしろゲームの規則そのものを変えることができるのではないか。

| いす取りゲームをいかに変えていくべきか |
|
|
▼
シンプルに考えれば、この3つの方法しかありえないことは自明である。
まず、「1」の「人を減らす」は無理。(ただし、数十年のちには、少子高齢化のために日本全体として「人手不足」になることが確実視されている)。
「2」の「いすを増やす」は、仕事を増やすことであり、具体的には、「景気の回復」、(特に野宿者のための)「公的就労の拡大」、「社会的起業」などが考えられる。
「3」の「いすを分け合う」は、ワークシェアリングである。
ゲームはその性質によって2種類に分類することができる。「競争ゲーム」と「協力ゲーム」とである。 「競争ゲーム」は、相手を負かすことを目的に行うゲームであり、例としては「テニス」「チェス」「サッカー」そして「いす取りゲーム」などがある。 「協力ゲーム」は、参加者が協力し合って結果を求めるゲームであり、例えば「蹴鞠」「伝言ゲーム」などがある。 |
▼
上の「競争ゲーム」「協力ゲーム」の議論は、アルフィ・コーンの「競争社会をこえて」などを参照している。
ただし、このゲームの2つの種類分けは実際にはなかなか微妙である。例えば、「チェス」や「テニス」のようなゲームでさえ、典型的な「競争ゲーム」の面と同時に、プレーヤーどうしの「協力」によって創造的な「棋譜」「試合」を作り出す、という「協力ゲーム」の面を持っている。
また、「野球」「サッカー」「リレー」のような競技の場合、チーム内では「協力ゲーム」を行い、チーム間では「競争ゲーム」を行う、という複合ゲームと言える。
ついでながら、「競争ゲーム」の例はいくらでも出せるが、「協力ゲーム」の例はなかなか出てこないだろう。
「いすを分け合う」ワークシェアリングは「協力ゲーム」の一種である。それは、「いす取りゲーム」と同じ条件の中で、異なる「ゲームの規則」を導入することによって成立する。 |
▼
「いすを分け合う」ことの利点は、参加者がいすを求めて「100倍、1000倍」の努力を払うような無駄な努力をせずに、全員があっさり(譲り合って)座ることができるということにある。「必ず何人かがいすからあぶれる」という不公平さは、これによって解消される。
▼
ワークシェアリングを導入し成功した例としては、オランダが知られている。「オランダ・モデル」として知られるこのシステムは、社会保険などのセーフティネットの完備したフルタイムの「正社員」と、セーフティネットが不完全で、短時間労働の「パート」という区分を「政府・労働者・使用者」の協力の下に解消し、多様な就労スタイルを実現することによって、失業率の大幅な低下と経済成長を実現させた。
この対極は、「(自由)競争」のもとで貧富の差が昂進し続けるアメリカ・モデルと言える。
むしろ、自由競争に基づくグローバリズムの中で南北問題が激化し続けるこの世界そのものがそうだ、というべきだろうか。
▼
ただし、「協力」が「競争」とくらべて倫理的に優越するものかどうかは疑問である。むしろ、その二つは互いに「補完」関係にあるものと言うべきかもしれない。
エスピン=アンデルセンの「福祉資本主義の3つの世界」「ポスト工業経済の社会的基礎」や柄谷行人他の「NAM 原理」にある議論だが、近代国家における「共同体」あるいは「(広義の)福祉」のあり方は、「資本」「国家」「家族=民族」の3つの極によって規定されている。「資本」が競争原理によって成立するとすれば、「国家」は税の「再分配」、「家族」は「相互扶助」によって成立している。「再分配」と「相互扶助」が一種の「協力ゲーム」であることは疑問の余地がない。しかし、それは「資本」に対して優越する価値を持つのだろうか?
▼
そして、ワークシェアリングは失業問題に対して決定的な「解」なのだろうか?
ワークシェアリングは「いす取りゲーム」の中でのいすの「わかちあい」と喩えることができる。だが、この競争原理に基づく「いす」自体が、日本の市場経済内部のものでしかない。つまり、その中で「わかちあい」をいくらしても、原理的に何も変わらない。つまり、ワークシェアリングは日本経済内部での「当座」の「局地的」な解決策にすぎない。
この「当座の」「局所的な」解と同時に、そうではない「永続的」で「グローバル」な解、少なくとも「中期的」で「対外的」な解が必要なのである。
▼
事実、フリーターによるワークシェアリング待望論は、「自分の今の生活スタイルを守る」ものとして言われることがある。だが、むしろワークシェアリングは、従来の「国家」「資本」「家族」の前提の上に成り立ったその「生活スタイル」をうち破り、様々な他者とつながり、新しい社会スタイルを作っていく、より広い「協力ゲーム」へのきっかけの一つであるべきなのではないだろうか。
なぜなら、第一にその守るべき「自分の生活スタイル」は、資本による世界的な南北格差と環境破壊の上に立って作られている。そして、「自分の生活スタイルを守る」ことは、あくまでその衣食住足りた狭い社会での後ろ向きな現状肯定でしかないように見える。
現状の世界への批判と変化の展望を持てない限り、従来の「国家」「資本」「家族」に依存した上で「自分のため」だけに働くという生活スタイルは保守化し、退嬰化することになるだろう。つまり、「競争原理に基づく資本への抵抗」は、「質的、量的にグローバルなわかちあい=協力ゲーム」にまでいくべきではないだろうか。
▼
「競争ゲーム」への抵抗としての「協力ゲーム」は、「国家」「市場」「家族」内部のゲームではなく、それら「ゲームの規則」の存在しない者どうしの「協力」でなければならないだろう。それは、いわば国家、資本、家族への「闘争としての協力ゲーム」(=共同闘争)となる。
それは、従来の「国家」「資本」「家族」のゲームの規則からは互いに不整合で異質とされていた者同士が結びつく「共闘」となる。とりあえずは、それを日本経済内部での「シェアリング=わかちあい」から、質的、量的により「広い」グローバルな闘争としての「わかちあい=協力ゲーム」へと言ってもよい。
この闘争に、日本内部の「南北問題」である野宿者問題が含まれることは言うまでもない。
▼この点については、ここではこれ以上は触れられない。「フリーター≒ニートひきこもり≒ホームレス――ポスト工業化日本社会の若年労働・家族・ジェンダー」(「フリーターズフリー」創刊号)で扱っているので、そちらを参照していただきたい。
■戻る