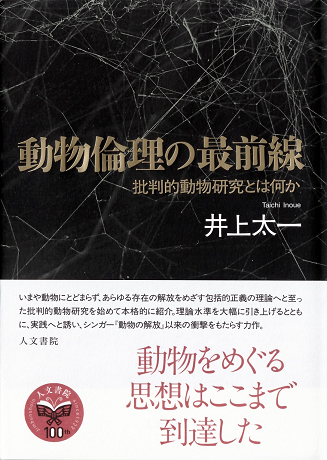書評・井上太一『動物倫理の最前線』(人文書院 2022)
2022/06/21
これまで動物問題に関する多くの重要な本の翻訳を行ない、日本での動物論の水準を格段に上げてきた著者による最初の書物――それだけでも大きな期待を抱かせるが、届けられた本書は、予想を超える充実した内容だ。
本全体は、「批判的動物研究」理論と動物問題の現状を踏まえた上で、シンガー、レーガン、フランシオンによる動物解放理論の検討を行ない、さらに「資本主義」「生政治」「家父長制」による動物への「構造的暴力」に対する批判を行なう構成になっている。ぼく自身、『いのちへの礼儀――国家・資本・家族の変容と動物たち』(2019)で動物問題の現状と動物倫理の検討を試みたので実感できるが、ここに示された著者の知的読解力と批判力は恐ろしいほどだ。
冒頭に「(批判的動物研究に基づく動物倫理を概説する)本書は国内初の試みであり、海外諸国と日本を隔てる動物倫理研究の溝を埋めることに少なからず貢献しうるのではないかと期待する」とあるが、その目的は間違いなく達成されたのではないだろうか。動物倫理に関する議論が不当に軽視されている日本で、膨大で重要な未邦訳文献の読み込みの上に練り上げられたこの本は、動物問題を語るため「ぜひとも読んでおかなければならない」必読書となるはずだ。
本書第1章「動物たちの現状」は、牛、豚、鶏などの工場式畜産での虐待を詳細にたどっている。ぼく自身も『いのちへの礼儀』の読者から「家畜の現状にもっともショックを受けた」という声を聞くが、ここで示される動物たちへの人間の支配のありさまには、あらためて言葉を失う。
ぼくが初めて知った内容に、「繰り返し妊娠を強いられる(乳用)牛たちは、実に二割から三割が屠殺場へ着いた時点でも身ごもっている」という事実がある。「その胎児は摘出されて採血室へ運ばれ、科学研究の細胞培養に使う血清を採取すべく、生きたまま心臓に針を刺され、死ぬまで血を抜き取られる(近年脚光を浴びている培養肉も、この血清を使って開発が進められてきた)」。
乳を採るために強制的に繰り返し妊娠させられ、そのあげくに体力を失って「廃用」にされ、主にハンバーグ用の挽肉となる牛たち。その牛たちだけでなく、胎内にいる胎児まで徹底的に「科学」利用され、「環境にやさしい」「屠殺なし」の培養肉の研究に使われる。そして、動物産業複合体によるこうした動物の徹底利用は、工場式畜産(『いのちへの礼儀』では「工業畜産」とした)のさまざまな場で行われている。
環境問題については、大規模畜産によって「世界の農地の8割超は畜産業と養殖業のために費やされ、アマゾンで進む森林伐採は9割超が放牧場の開発を目的に行われている」という事実がある。また、「底引き網漁は今や世界最大の捕殺量を誇る漁法となり、毎年これによって破壊される海域面積は世界の森林伐採地の一五〇倍、アメリカ合衆国本土の三倍にも達している」。
環境破壊の最大要因の一つが「工場式畜産」なのだ。これにアプローチし解決しなければ、「地球にやさしい」といった言葉は意味をなさない。こうした現状を知れば知るほど、人間は、そこまでして動物の肉や乳、卵を食べなければならないのか、と考えざるをえなくなる。
第2章「道徳哲学」では、シンガー、レーガン、フランシオンなどの理論が検討される。フランシオンは「廃絶主義」としてこのように言う。「全ての動物製品が苦しみを含み、全てのそれが死を含み、全てのそれが不正を含む。脱搾取は道徳的使命にして、私たちがなさねばならないこと、妥協してはならないことである」(強調削除)。
事実、著者は自ら「脱搾取」としてのヴィーガニズムを実践している。「工場式畜産」の問題を批判しながら、その製品を消費するとすれば、それは単なる言行不一致だからだ。ぼく自身は、外食での困難からヴィーガンにはなれず中途半端なフレキシタリアンだが、肉、卵、牛乳は買わない生活を続けている。
ただ、個々人が消費者として「工場式畜産」商品をボイコットするだけでは問題は解決しない。人間と動物の関わりには、資本主義、生政治、家父長制という歴史的、構造的な問題が交差し、「個人の変革と社会構造の変革は車の両輪と考えられる必要がある」からだ。
「工場式畜産」は20世紀後半に拡大してきたが、本書では「動物搾取を推し進める歴史的な原動力は経済であり、その営為が生む富は一握りの特権階級に吸収される」(ナイバート)という視点から、動物解放運動を資本主義批判として捉える視点が強調される。
そして、ここから本書は、第4章「ポスト人間主義」で「人間中心主義、生政治」の検討を行う。「人間中心主義」は西洋哲学の歴史と同じように古いが、20世紀後半になり、デリダ、アガンベンなどの思想家が「動物」に注目し、新たな動物への思考を提示してきた。
著者は、デリダの言う「肉食男根ロゴス中心主義」、つまり西洋では「肉食」と「理性」と「男性」性が一体化し、それを中心に社会的に強固な抑圧を創り出してきたという指摘に注目している。さらにフーコーらが展開した「生政治」の概念が、人間だけでなく動物に対して、たとえば工場式畜産をはじめ、動物園や水族館、さらに絶滅危惧種の保護という形であからさまに適応されてきた事実を指摘する。
ところで、いままで挙げてきた人名はすべて男性だった。一般にも「動物擁護も男性知識人が主導してきた運動および学問」であるような印象があるかもしれない。それに対して、第5章「フェミニズム」では、「動物擁護の思想・理論・運動は、今も昔も女性たちが中心となって形づくってきた」事実が示される。そこには、「人間女性を抑圧する父権制の論理は、同時に動物搾取の思想的・物質的基盤である」という背景がある。「したがってフェミニズムが人間女性だけの正義であってはならないのと同様、動物擁護は人ならぬ動物たちだけの正義であってはならない」。
これはフェミニズムと動物倫理だけの問題ではない。動物の解放は、貧困やレイシズム、セクシャル・マイノリティなどの解放運動への理解と協力の上で行なわれる必要があるのだ。終章「総合的解放」では、社会的抑圧の多様性と交差性への意識化を通して、さまざまな解放運動が抑圧システムに対する「共闘」を行なうという、人間と動物の解放運動のビジョンが示される。
そこで強調されるのは「寄り添い(ケア)の倫理」となる。従来の動物解放論、動物権利論では、「感情」に基づく議論でなく「理性」に基づく理論が優先してきた。その偏りを批判し、本書は、動物という他者の苦しみに「動かされる」こと、それによって自己の「外」へと抜けだし、それぞれ異なる存在どうしが尊重し合い、解放される社会を展望しようとする。
このように、本書は動物倫理を中心に膨大な文献の検討と鋭利な批判力によって、あるべき「人間―動物関係」をみすえようとする希有な書物となっている。間違いなく、日本で書かれた動物倫理に関する最高の本だろう。
ただ、その上で、意見の相違を感じる点もある。そのいくつかについて、今後の議論の発展のため、触れておきたい(なお、以下の議論は『いのちへの礼儀』で書いた内容に多く触れている)。
たとえば、本書ではデリダが示した「肉食男根ロゴス中心主義」の指摘が重要視される。「肉食男根ロゴス中心主義は今日もなお健在であり、人間の理想像から漏れ落ちる膨大な『他者』を主体の地位から排除する仕組みとして機能し続けている」。こうした志向が、「旧約聖書」に生々しく書かれた「動物の生け贄」以来、ユダヤ・キリスト教文化の核心的なドグマとして生き続けたことは確かだろう。しかし、これは牧畜生活の中で肉食を続けてきた西欧社会にあてはまっても、日本にはあてはまらない。
『いのちへの礼儀』で詳しく触れたが、西欧では家畜の糞尿による堆肥で畑や牧場の土を肥やし、そこで育った草や果樹を家畜が食べるというサイクルの創出によって農耕と牧畜を一体化させた。しかし、日本のような稲作水田では、家畜の堆肥は必要とされない「水耕稲作と畜産業の相性の悪さ」があった。
そして、現在も毎年宮中で行なわれている「新嘗祭」(にいなめさい)で、天皇は新米など供物を捧げる「神人共食」を行なう。米は天皇と神を繋ぐ「清く尊い食べ物」、農作物の中で「聖域」にあるものとして別格扱いされている。そして、それと反比例するように、肉食は「罪」や「穢れ」という意味を持たされるようになっていった。そこには、人口増加と水田の膨張、森林の荒廃による野生動物の減少によって、民族として肉食を続けることが割に合わない、つまり不合理だったという背景があった。これが、1200年に及ぶ「肉食禁止令」として国策化されていく。日本の場合、その地理的条件から、「肉」ではなく「米」が政治的・経済的・宗教的な焦点に存在する象徴的な「主食」となったのだ。
その意味で、日本ではデリダの言う「肉食=ファロス=ロゴス中心主義」ではなく「米食=ムラ社会=天皇制中心主義」が成立したと言える。これは、外国人差別をはじめ、日本で「今日もなお健在であり、人間の理想像から漏れ落ちる膨大な『他者』を主体の地位から排除する仕組みとして機能し続けている」。したがって、われわれは、デリダの議論を参考としつつも、「日本ではどうなのか」を考えなくてはならない。そうでなければ、肉食と動物倫理の問題について、デリダの議論を日本において受け止めたことにならないし、意義のある国際的な議論は成立しない。
そして、現代の日本の大規模畜産の特異性は、近代に入って日本が「富国強兵」政策(2022年、引き続くデフレとロシアのウクライナ侵略を受け、日本では国策「富国強兵」がそのまま復活した…)のため、「肉食」を産業として急激に大規模導入したため、はじめから家畜を「食材」としかみなさなかったという点にある。そしてそれが、現在に至るまで、食用動物について、国際的に見ても「酷薄」な態度を日本社会にもたらしたのではないか。こうした歴史的条件の考察は、日本で動物倫理と動物解放を考える上で欠かせないと思う。
それに関連して、本書は菜食フェミニスト、キャロル・J・アダムズの『肉食という性の政治学』を紹介している。アダムズは肉食と欧米の男性中心主義の結びつきを考察し、「肉食は男性支配に不可欠な要素である。したがってベジタリアニズムは、父権的文化にとっては不・快のサインとして作用する」(『肉食という性の政治学』鶴田静訳 原著1990)とした。彼女はフェミニズムとベジタリアニズムを両立させる運動によって、男性中心社会を変革する必要を訴え、フラント・ウィナントの詩「米を食べ 女たちに信頼を」を引用し、「父権的な消費を不安定にするのは、米を食べ、女性を信頼することである」と言う。
しかし、この「米を食べる」という戦略は、翻訳者の鶴田静も指摘するように、米が特に高位者の「主食」であり「米食=ムラ社会=天皇制」中心主義にある日本では、むしろ体制追認の意味を持ってしまう。たとえば岩崎正弥は、米食を悲願とした近代日本は「米食共同体」であり、そこには「日本米と日本人の心性が密接に関係すると捉えていること。日本精神や大和魂の土台こそ日本のコメなのだ、という主張に端的に現われている」としている(『食の共同体 動員から連帯へ』2008)。近年続いている、農林水産省と文部科学省による学校給食での「米食」推進も、そうした背景と政治的に無縁ではない。
その意味で、日本では「肉食」の問題は「米食」の問題との関連抜きで考えることができない。実のところ、『肉食という性の政治学』での議論は理解できない飛躍が多く、個人的にはついて行けないものを感じるが、ここでも、アダムズの考察を参考にしつつ「それでは日本ではどうなのか」を考えなければならないだろう。それは、日本で動物倫理を考える者に課せられる責任なのだ。
また、「寄り添い(ケア)の倫理」について、本書は理性的な批判に終止したシンガー、レーガンらの議論を相対化して、「感情否定は暴力の元凶である。人々が憐れみや思いやりを捨て去った時、他者への横暴が始まる」(p308)と、「感情の復権」を語っている。抽象的な「原則」「権利」だけでなく「具体的な文脈や関係にもとづく倫理」を重んじるというこの批判は確かに重要だ。『いのちへの礼儀』でも、シンガーの議論には具体的な「動物との出会い」を回避し、距離を置こうとする面があると言った。動物工場や実験場で虐待される動物たちの解放を求めるシンガーは、苦しみ無視されていた動物たちに理論的に近づき、その「隣人になった」。しかし、シンガーに、自身が動物が現実として出会い、感性を揺さぶられ「解放」される関係性が欠落している面がある、ということだ。その意味で、「感情の復権」が言われる方向は理解できる。だが、そこで重要なのは「感情」なのか、という疑問がある。
社会運動の中で、「感情を出す」ことの重要性は、特に女性たちからたびたび語られてきた。理論を語るだけではなく、具体的な抑圧や差別、葛藤にある個々人の「感情」から出発することこそ重要だ、という意味だ。
しかし、差別に関わる議論をしていた時、活動仲間の一人が「感情ではなく感性をぶつけあうことが重要だ。感情と感性を混同してはいけない」と言ったことがある。これには納得させられた。
「感情」は個人的なもので、「怒り」も「喜び」も「憐れみ」その人の特性によって大きく違う。社会運動の中で「感情をぶつけあう」ことが、多くの場合、建設的にならないのはそのためだろう。
しかし、「感性」は、「感情」と同時にそれを自ら批判的な捉え直し、鍛え直す「省察」の面がある。だから、人は「感性」を他者との関わりや議論で鍛えることができるし、社会的な問題の中で「感性」をあらたに作り直すこともできる。
こういう事を言うのも、すでに「感情」を社会的問題の基準とする傾向が強いからだ。たとえば、差別問題で「不快な思いをさせた」という事が問題にされたり、「相手が不快に思えばハラスメント」と言われることもある。
しかし、差別やハラスメントは「された相手がどう感じたか」という「感情」「感覚」だけの問題ではない。そうだとすれば、相手が問題と感じなければそのままで構わない、ということになりかねない(これは、「感覚」についてシンガーが陥った深刻な問題でもある。シンガーは、家畜の鶏に「脳」がなければ痛みを感じないから問題を解決できるのではないか、と問われ、そうかもしれない、と答えたのだ)。
逆に、「感じやすい」人(の中には、自分の痛みには敏感だけど、他人の痛みには鈍感な人もいる…)が過剰に周囲を糾弾する、ということも起こりうる。しかし、あくまで、社会構造の中でその言動がどのような問題を持つのか、ということが重要なのだ。そこでは、「権利」や「正義」の概念が依然として有効な意義を持つ。
その意味で、社会問題を語る場合、「感情」より「感性」が妥当だろうと思う。ただ、ぼくはそれを「尊厳」と言うべきではないか、と思うようになった。トム・レーガンは『The case for animal rights』で、「苦しみ」をもたらし個体の幸福を大きく損なう行為を「加害」(harm)とし、さらに「剥奪」(deprivation)について語った。『いのちへの礼儀』では「尊厳の剥奪」という表現を使ったが、「剥奪」は動物(や人間)の性質や可能性が奪われる状態を言う。「動物の解放」は「痛み」(pain)、「苦しみ」(suffering)と同時に、なによりも尊厳の「剥奪」(deprivation)からの解放としてあるのではないか、ということだ。
例えば、主体が「痛み」や「苦しみ」などの「感情」を感じないまま「尊厳を剥奪」される状態はありえる。しかし、それをわれわれは深刻な社会問題として考えなければならない。そして、われわれは他者への「憐れみや思いやり」(p308)を持つべきかもしれないが、それは決して個人的な「感情」の問題ではない(そもそも、「憐れみや思いやり」というのは「上から目線」な感覚ではないだろうか)。むしろそれは、異質な存在どうしの「出会い」において起こる事柄で、「自分と他者の尊厳をともに尊重したい」という社会的な問題なのだと思う。
「感情」は主観的なものだが、われわれはそれを常に社会的に捉え直す必要がある。その意味で、「具体的な文脈や関係にもとづく倫理」の場合にも、「感情」よりも「感性」を、そして「尊厳の尊重」を重んじる方が適当ではないかと思う。それは、本書でパトリシア・マコーマックを引用して言われた「存在者間の差異に向き合い、その開花を認めること」と重なるだろう。
そして、本書の構成では「資本主義」「生政治」「家父長制」による動物への構造的暴力が語られるが、そこで欠落しているものとして「家族」の問題があるのではないか。「フェミニズム」の章で詳しくたどられるように、「女性・動物・自然の抑圧はいずれも父権性の思想を反映し、互いを強化する関係にある」(P285)。確かに成人男性からの女性の抑圧・暴力と動物へのそれは大きく重なっている。
だが、「家族」の中にあるのは「男性と女性」というカテゴリーだけではない。特に「こども」の存在は欠かせない。そして、動物は、父権性の中で「女性」扱い以上に「こども」扱いされてきたのではないだろうか。
われわれは、家畜動物や愛玩動物、そして野生動物までが「こども扱い」されるのを見聞きする。そこでは、「こども」は「管理下に置くべき存在」「自由に扱ってよい存在」「可愛がる存在」などとして、つまり「下」の存在として扱われている。男性も女性も、ペット(コンパニオン・アニマル)を「うちの子」とよく呼んでいる。たとえ老齢になっても犬や猫を「子ども」扱いする姿勢は、その「尊厳」を尊重するというより、あくまで「自分の自由になる存在」として扱っていることを示している。
したがって、動物問題を考える場合、「こども」の視点を考えることは必須だろう。つまり、「動物の解放」は「こどもの解放」と同時でなければならないし、両者は「共闘」しうる。
たとえば、肉食を否定した多くの人間は「こども」だった。『いのちへの礼儀』で紹介したように、ナタリー・ポートマンは「9歳の時に見た鶏のレーザー手術のドキュメンタリーを観て以来、肉も魚も口にしていない。ただ動物が好きだから価値観に従うまでです」と、そして『アナと雪の女王』でアナの声を演じたクリスティン・ベルも「ハンバーガーと愛犬を切り離して考えることがどうしてもできなかった」「犬は食べないのに、牛は食べられるという理屈が理解できなかった。動物はみんな同じなのに」と11歳からベジタリアンになった。もちろん、こうしたこどもは日本でも多い。
ぼくは思うのだが、ベジタリアンやヴィーガンの立場は、こうした「こども」たちによって、その正当性をもっともよく示されているのではないだろうか。難しい(ややこしい)理論に関係なく、このこどもたちは「動物を殺して食べるのは間違いだ」と普通に考えて実践したのだ。われわれは、こうしたこどもたちの声に対して誠実に答え続けなければならない。
「家族」の視点が重要なのは、もう一つ理由がある。それは、20世紀後半、特に21世紀になり、「家庭動物」であるペットの位置が劇的に変化したからだ。
かつて、犬は番犬として犬小屋で暮らし、猫は放し飼いで近所を勝手に歩き回ってエサを探していた。家であげるエサも人間の残飯があたり前で、ペットフードなどよほどのお金持ちでないと買ったりしなかった。しかし、犬や猫は次第に「単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナー」になった。ペットの葬儀代、ペットのしつけ教室代、医療費、アクセサリーなどの多額の消費はその指標になっている。
これはいろいろな相談でよく聞くことだが、「ペットの犬や猫が死んだときは、親(あるいは子ども)が死んだ時より悲しかったし、衝撃が大きかった」と言われる。これにはいくつかの要因が考えられるが、いまやペットの存在が「家族以上」に感情的に重要になっているのだ。
本書では「動物解放は資本主義や国家権力への抵抗と一体でなければならない」と言われている。以前に「資本と国家への対抗運動」と謳われた柄谷行人の『NAM』についても思ったが、そこでなぜ「家族への対抗運動」は語られないのだろうか。エスピン・アンデルセンなど、多くの社会分析が「市場・国家・家族」という「内的因果関係に立つ三極構造」について語っている。そして 現状の「家族」がきわめて抑圧的な装置となっていることは多くの人が実感している。にもかかわらず、運動理論の多くは「家族への対抗運動」について語ろうとしない。
ここであらためて思い出されるのは、レーガンによる「ボートの比喩」である。「難破した船から人間4人と犬一匹がボートに脱出した。ボートは小さく、最低1人または1匹をボートから放り出さなければ全員が死んでしまう。人間を放り出すべきか、犬を放り出すべきか?」
これについて、レーガンは「犬を放り出すべきだ」と言う。しかも、1匹ではなく多数の犬(原理的には何百匹の犬でも)その結論は変わらないと言う。
本書はこの比喩について、「現実の人間動物関係を考えるうえで何らの示唆も与えない」(P96)としている。しかし、ここには「家族―動物」関係の変容と、現状の動物倫理との大きな「齟齬」が露呈していると思う。
動物解放論も含め、あらゆる哲学や倫理は「動物より人間を救うべきだ」と答える。では、現実のわれわれはどう行動しているのか。
日本ではペットの延命治療のために百万円近い医療費を出す人もいる。そこまででなくても、2021年のペット医療、ペット美容、ペットホテルなどペット関連商品の国内市場は(前年より4.3%増え)5271億円となっている。一方、いま、栄養失調やそれに伴う免疫低下、感染症などで死亡する5歳未満のこどもは世界で1日に1万4000人(2019年)にのぼる。約5000円でひとりのこどもに1年間の給食を提供することができるため、世界各地から食糧援助や資金援助がおこなわれている。
「動物より人間を救うべき」なら、われわれは犬や猫に使っているお金を多くのこどもたちの命を救うために使っているはずだ。しかし多くの人は、飢えに苦しむこどもたちより、自分のペットの医療やペットフードやシャンプーを優先している。なぜなら、犬や猫は愛着ある「家族」だが、飢えているこどもは「他人」だからだ。つまり、現実のわれわれは犬でなく人間をボートから放り出し続けているのだ。
シンガーは「救いがたいスピシーシズム(種差別)とよべる唯一の立場は、生存権の境界を正確に生物種の境界と一致させようとする立場である」と言った。だがこうした「種差別」は、「家族ペット」という現実の前では完全に逆転している。「生存権の境界」は、現実には「種」ではなく「家族」の境界で決められているのだ。
これは、「寄り添い(ケア)の倫理」が持つ問題にも関わる。ケアの倫理は「身近な他者」、たとえば家族(ペット)との関係に焦点を置きがちで、「遠い他者」に対しては一定の困難を持つ。そこでは、「公平性」などの視点の導入がどうしても必要なのだ。動物倫理の場合、「寄り添い(ケア)の倫理」だけでは現実に対応できないと思うのは、こういう面にもある。
「国家・資本・家族」の変容の中で、われわれと動物との関係も変化し続けている。それに対応して、動物倫理も変化していかなければならない。もしかしたら、「資本」に関してはシンガーの動物解放論が有効、「資本」「国家」についてはレーガンの動物権利論が有効、「家族」については「寄り添い(ケア)の倫理」が有効、という複合関係が考えられるかもしれない。
この問題について、著者は「現代思想」での伊勢田氏の対話で、「差異の論理」として「他者の数だけ倫理的応答がある」という方向を示唆している。しかし人間と同様、動物についても「資本・国家・家族」という構造的な分析から現実に適した倫理を構想する、という方向が妥当性を持つように思う。動物問題の複雑さと、理論的な整合性との両立を求めるには、それしかないのではないだろうか。これは、ぼく自身が考えなければならない課題でもある。
著者の井上太一さんとは何度か対談し、個人的にもやりとりを続けている。対談を聞いたり読んだりした方、そして本書と『いのちへの礼儀』を読んだ方にはおわかりのように、われわれの意見は近い面もあるが、相当に異なる面が多い。たとえば、野生動物への対応、ペット問題への対応、さらに現代の小規模(伝統的)畜産や狩猟問題のいくつかの点について、意見の合致は難しいだろう。しかし、著作家、翻訳者としての井上さんへの尊敬は、大きくなるばかりだ。最初に触れたように、日本では動物倫理に関する議論が不当に軽視されているが、現代日本は井上太一という希有な人物を持ったことを誇るべきだと思う。
ある意味で、この書評は、井上さんが『いのちへの礼儀』について書かれた書評への応答である。『いのちへの礼儀』が動物倫理に関わる人たちからほぼ無視される中、井上さんの書評は大きな心の支えとなった。
井上さんはそこで「理論的洞察と実践的関心を兼ね備えたこの探究は間違いなく、人間動物関係の倫理をめぐって建設的な議論を喚起する力を持つ。(…)本書が市井と学界の区別なく、多くの人々に読まれることを願いたい」と言ったが、ぼくも、今後の動物倫理の建設的な議論のため、そして動物解放に関わる活動のため、『動物倫理の最前線』が広く読まれ、議論を呼ぶことを期待している。
■HOME